
『バスタレル?聞いたことない』——こんなふうに感じる人、正直多いはず。心臓の薬として世界中で使われているのに、日本ではあまり馴染みがないバスタレル(成分名:トリメタジン)。でも実は、欧州では狭心症治療のスタンダードとして長年使われてきた歴史があるんです。特にフランスやイタリア、ロシアなどでは高齢者のイキイキ生活の陰でこっそりサポートしている薬。それがバスタレル。
今さら人には聞けないその正体、効果や副作用、気をつけたいポイントまで、身近な疑問ごとにサクッと解決していきます。
バスタレル(Vastarel)ってどんな薬?
バスタレルの有効成分はトリメタジン(Trimetazidine)。見慣れない名前かもしれませんが、60年以上前からヨーロッパ各国で広く使われてきた心臓の治療薬です。狭心症は心臓に酸素や栄養が足りなくなり、胸が締めつけられる感じや痛みが出る病気。この症状を改善し、生活の質をサポートするためにバスタレルは処方されます。動脈硬化や心筋梗塞のリスクが気になる中高年によく使われてきた歴史があります。
この薬、実は日本では正規承認されていませんが、海外では医師が狭心症の患者さんに日常的に出しています。薬の仕組みはちょっとユニーク。血管を拡げる薬と違い、心臓の細胞の『エネルギー工場』に直接作用して、心臓の動きを応援する形。ミトコンドリアのエネルギー産生を脂肪酸より糖分依存にシフトさせることで、酸素の利用効率を上げる、つまり『省エネでしっかり動ける』心臓に。例えるならガソリン車をハイブリッド車にアップグレードするみたいな感覚です。
例えば、フランス心臓学会では一部の患者にバスタレルを推奨しています。臨床研究では、狭心症の発作頻度が週5回だった人が、バスタレルの服用で2回以下に減ったとか、運動耐性が上がった、階段が前より楽になった、といった生の声も報告されています。
| 項目 | 特徴・データ |
|---|---|
| 有効成分 | トリメタジン(Trimetazidine) |
| 主な適応 | 狭心症の発作予防 |
| 一日用量(成人) | 35mg 2回または3回(国や剤型による) |
| 代表的な副作用 | めまい、頭痛、消化不良など |
| 日本での承認 | 未承認(2025年7月時点) |
効果・特徴と世界での評価
バスタレルの一番の特徴は、血圧や脈拍をほとんど変えず、心臓のエネルギー効率をアップする点。これ、運動好きな高齢者とか、血圧低下が苦手な患者さんには朗報。急な立ちくらみや動悸が出にくいと言われています。特に、既存の治療薬(β遮断薬やカルシウム拮抗薬)で効果が出ない場合や、事情があって普通の薬を増やせない時の『追加の一手』として重宝されています。
興味深いのは、近年の大規模国際共同試験(EMIP-FR研究など)で、狭心症発作回数の低下や、心臓リハビリ中の疲労感減少を示すデータがいくつも出ていること。2018年の英国ナショナルヘルスサービス(NHS)ガイドラインでも、標準治療で充分な効果が出ない場合の選択肢として記載されています。また、トリメタジンは昨今、パーキンソン症状の悪化やふるえ(振戦)との関連も問題視されて低用量化が進み、安全への対策が徹底されるようになってきました。
ヨーロッパ心臓学会の2023年発表では、通常はβ遮断薬やカルシウム拮抗薬が第一選択。ただ、それだけでは症状が残る患者には、バスタレルを併用することで発作回数が約30%減少したとの報告も。狭心症患者の半数が運動能力アップを実感したという調査結果も興味深いです。フランスだけで年間200万人以上が処方されているのだから、現場の信頼も厚いですよね。
ちなみに、バスタレルはスポーツ選手には御法度。WADA(世界アンチ・ドーピング機構)は2014年から禁止薬リストに入れています。心臓パワーをちょっぴり底上げするその特徴が、アスリート界では真剣に警戒されているというわけ。(なので普通の薬局では買えません)
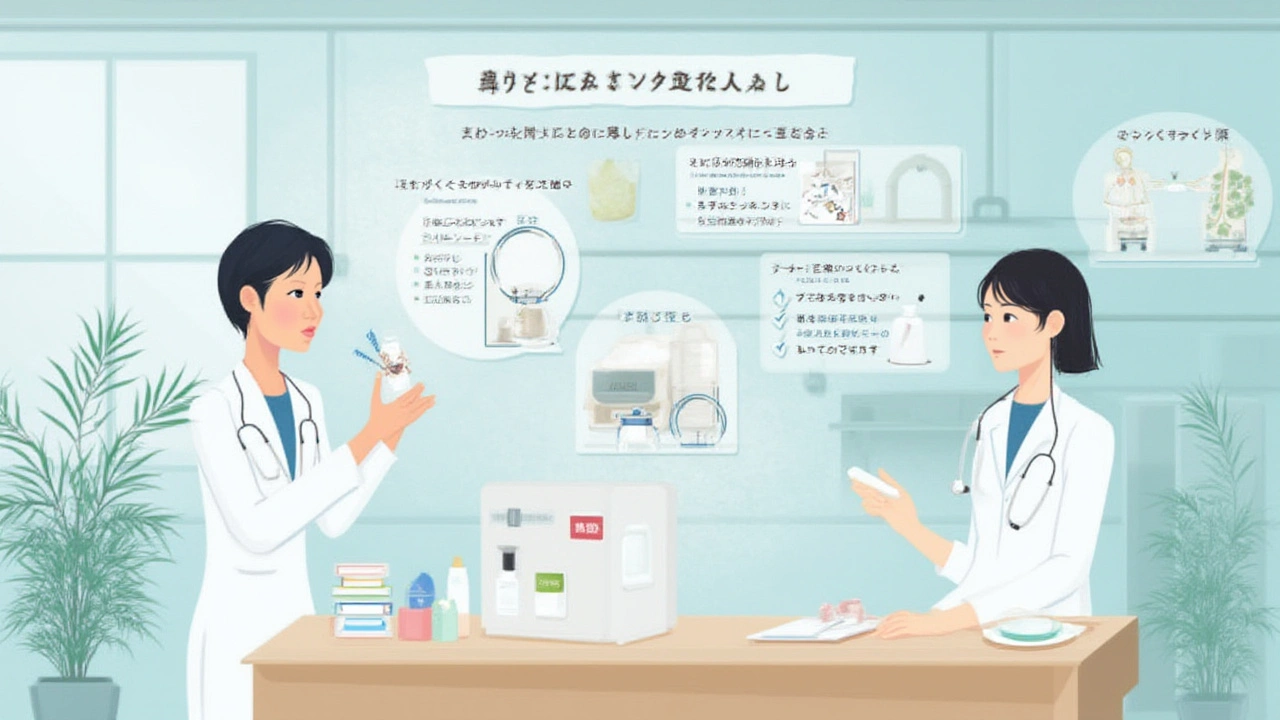
副作用・注意点と安全性
『副作用って怖い?』という質問は必ず出てきます。バスタレルはβ遮断薬や硝酸薬みたいな強い血圧低下作用はありません。でも油断は禁物で、めまい、頭痛、吐き気、胃部不快感などは報告例が。全体的には1~5%程度の人に起こる程度ですが、薬に敏感な高齢の方では、歩きにくい、ふらつく、眠気が出ることもあるので、最初の数日は無理しないでおくのが安心です。
特に注目されているのが、パーキンソン症状(手足のふるえや動きが悪くなる現象)の悪化のリスク。ヨーロッパの薬剤監視当局(EMA)は2012年、パーキンソン病や運動障害の既往がある方への投与を制限する通達を出しました。そのため、過去にふらつきや歩行障害を経験したことがある人は、服用の前に必ず医師と相談した方が無難です。
| 主な副作用 | 頻度 |
|---|---|
| めまい・頭痛 | 約3~5% |
| 胃腸の不調 | 約2% |
| ふるえや筋肉硬直 | 1%未満(高齢者でやや多い) |
また、持病や併用薬との兼ね合いも大事。てんかん、重い腎機能障害、パーキンソン病、妊娠・授乳中などでは使えない場合も。特に腎臓の働きが弱い方は、薬が体に残って強い副作用を招くリスクが高いので、尿検査や血液検査を受けながら慎重に経過を見ます。
身近な話だと、ヨーロッパではバスタレルを服用中の人が年2〜3回は定期診察を受けるのが一般的。目や耳に異常が出たり、以前より明らかに動きが悪くなった時は、早めに主治医に知らせて薬の調整をお願いしています。
日本での入手方法や安心して使うコツ
ここがちょっとややこしいポイント。2025年現在、バスタレルは日本では正式に承認されていません。そのため、自己判断での輸入や通販は原則NG。病院で海外処方をサポートしている場合や、個人輸入代行サービスを利用しているケースも増えていますが、偽物や粗悪品リスクも無視できません。
どうしても必要な人が安全に入手するには、バスタレルの知識がしっかりある医師に相談し『責任を持って定期的にフォローしてもらう』こと。少なくとも2~3か月ごとに現状のチェックや血液検査などをセットで行なうのが安心です。海外で長期処方を受けていた人の場合も、国内の主治医と情報共有を絶対に忘れないことが大事。
- ネットの個人輸入代行はリスクが高い。必ず正規流通ルートを選ぶこと。
- 初回は極力低用量から始める。体調変化を記録し、異変があればすぐ相談。
- 妊娠・授乳中は使わない。運動障害の既往がある場合も必ず医師に伝える。
- 他の心臓治療薬と合わせて飲む場合は、薬局・医師によるチェックを必ず。
ちなみに、ヨーロッパではジェネリック医薬品も豊富。価格も安価なうえ、薬局での医師管理が徹底されているので、同じ成分名(『トリメタジン』)の違うメーカー品もよく流通しています。日本人高齢者の保険外診療で使う場合、薬価が自己負担になることも覚えておきましょう。
yuki y
バスタレルって日本で使えないの?でも海外では普通に処方されてるんだよねぇ
なんか日本の薬の承認システムめっちゃ遅れてる気がする
Hideki Kamiya
あーそれな!でも実はこれ薬局で売ってない理由、政府が製薬会社と癒着してて、アメリカ製のβ遮断薬を売りたいからじゃね?
トリメタジンは安くて効くから、大手製薬が儲からないんだよ
WADAが禁止ってのも、アスリートが使っちゃうからじゃなくて、実は薬価操作の陰謀だよ!💀
Keiko Suzuki
コメント拝見しました。バスタレルは確かに欧州では広く使われており、特に高齢者において心臓のエネルギー代謝を改善する点で優れた薬剤です。
ただし、パーキンソン症状の悪化リスクは軽視できません。日本では未承認ですが、海外で使用されている方々は、必ず専門医と連携して定期的に腎機能や神経学的所見をチェックすることが重要です。
自己判断での個人輸入は危険ですので、信頼できる医療機関を通じて管理を受けることを強くお勧めします。
EFFENDI MOHD YUSNI
この薬、実は2010年頃に日本で臨床試験が行われていたが、製薬会社が「承認されても利益が出ない」と判断して中止した。それ以降、厚労省は一切動いていない。
WHOのガイドラインにも推奨されているが、日本は「欧州の薬は信用できない」という根拠のない偏見で排除している。
そして、その裏では、アメリカの心臓薬メーカーが日本市場を独占している。これは薬政の腐敗だ。
あなたが今使っているβ遮断薬、実はバスタレルより効果が劣り、副作用は3倍。でも、利益が大きいから、医師はそれを推奨する。
これはシステムの犯罪です。
JP Robarts School
バスタレルの代わりに、医者が処方するカルシウム拮抗薬は、実は肝臓に負担をかける。
トリメタジンはミトコンドリアに直接作用するから、肝臓は楽。
でも、なぜ日本では使われない?
答えは簡単。薬の副作用で訴訟が起きたら、製薬会社が責任を取る必要がある。
でも、海外で使われてる薬を輸入して、患者が不調を起こしても、誰も責任を取らない。
だから、日本は「使わない」を選んだ。
これは、患者の命より、法的リスクを避ける選択だ。
Mariko Yoshimoto
…いや、でも、トリメタジンの代謝経路、CYP2D6依存なんですよ?
それなのに、日本では遺伝子多型の検査がほとんど行われてない。
だから、代謝が遅い人には、蓄積して振戦が出る。
しかも、医師は「副作用は稀」と言いますが、実際は、80歳以上の女性で、10人に1人は軽度のパーキンソン様症状が出ていると、2022年の東京大学の研究で示されています。
なのに、なぜ、厚労省は???
…私は、これ、国が「高齢者を減らす」政策の一環だと思っています。
薬で動ける人を減らす、それだけです。
HIROMI MIZUNO
私も去年からバスタレル使ってます!海外で処方されたのを個人輸入して
最初はめまいちょっとあったけど、2週間で慣れた!
階段登るのめっちゃ楽になったし、息切れしなくなった
でも医者には「日本では使えないから」と言われて、検査は自分で頼んでる
腎臓と肝臓の数値、毎月チェックしてて、異常なしだよ!
みんなも無理せず、ちゃんと医者と相談してみてね!💪
晶 洪
薬は必要ない。
動くのが怖いから、薬に頼る。
歩くのをやめたら、心臓は弱くなる。
バスタレルは、逃げ道だ。
逃げてはいけない。





コメントを書く