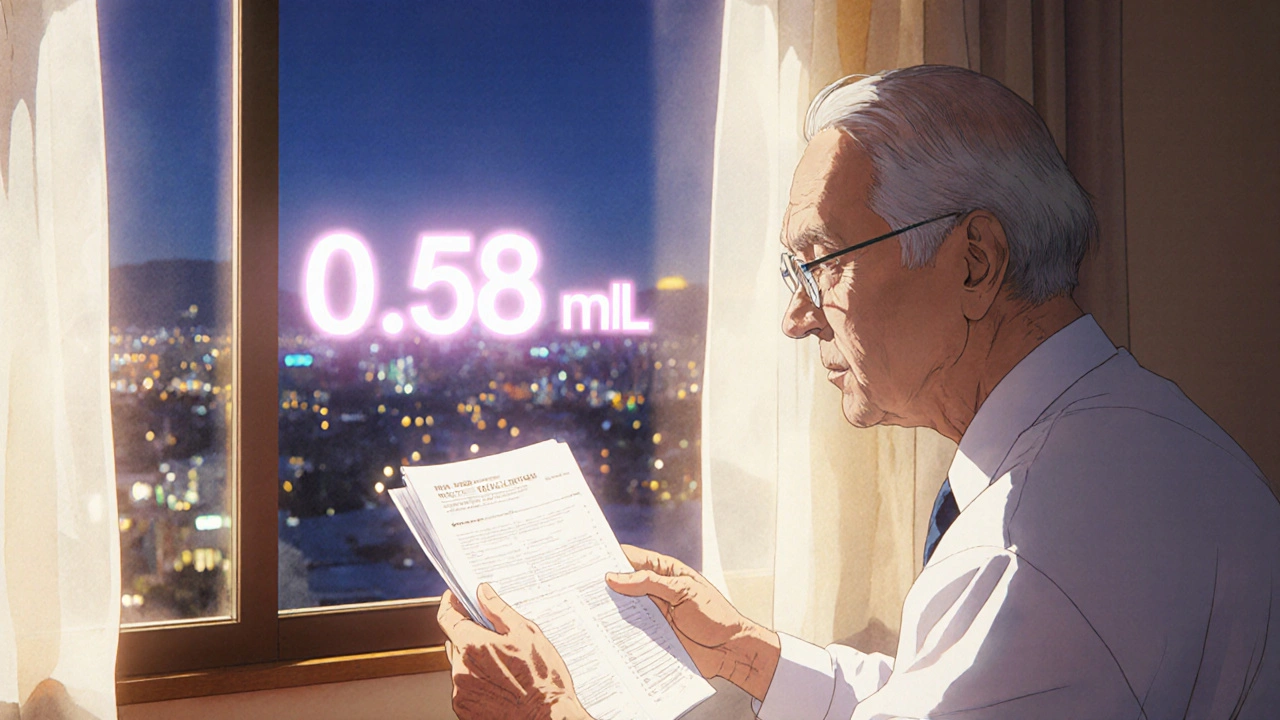
双極性障害の治療で、リチウム炭酸塩は70年以上にわたり信頼されてきた薬です。ジェネリック薬が広く使われるようになっても、その効果と安全性は、血中濃度に大きく左右されます。薬の名前が変わっても、血中のリチウム濃度が一定でなければ、発作が再発したり、重い副作用が出たりするリスクがあります。
なぜ血中濃度がこんなに重要なの?
リチウムは、血中濃度が0.6~1.2 mmol/Lの範囲で効果を発揮します。この幅がとても狭いのです。0.5 mmol/Lでは効きが弱く、1.5 mmol/Lを超えると吐き気、ふらつき、手の震えが起こり、2.0 mmol/L以上になるとけいれんや心臓の不整脈、昏睡に至る可能性があります。
この「治療指数が狭い」性質は、ジェネリック薬を使うときに特に注意が必要です。同じ量のリチウムを飲んでも、メーカーによって吸収の速さや体内での動きがわずかに違うのです。たとえば、あるジェネリックは1時間で血中に溶け出し、別のものは4時間かけてゆっくり吸収されます。その結果、同じ処方でも、血中濃度が10~20%も変わるケースがあります。
ジェネリックとブランド薬の違いは?
「Camcolit」「Priadel」などのブランド薬は、ゆっくり効く持続放出型(ER)が主流です。一方、ジェネリックには即効型と持続放出型の両方が存在します。日本や欧米では、持続放出型が75%以上を占めています。なぜなら、1日1~2回で済み、血中濃度の波が穏やかで、副作用が少ないからです。
しかし、2024年の研究では、同じ持続放出型でも、ブランド薬とジェネリックの間で血中濃度に有意な差が出た例があります。ある患者は、ブランド薬からジェネリックに切り替えた直後に、血中濃度が1.32 mmol/Lまで上昇。これは中毒の手前です。別の患者は、逆に濃度が下がって、うつ状態が再発しました。
FDAやEMAは、ジェネリック薬が「生物等価性」を示せば、同じ効果があると認めています。つまり、血中濃度の曲線(AUC)と最大濃度(Cmax)が、ブランド薬の80~125%の範囲内ならOKです。でも、この範囲は「平均的には同じ」ことを意味するだけで、個々の患者に同じ影響を与えるとは限りません。
血中濃度の測定は、いつ、どうやる?
血中リチウム濃度を正確に測るには、タイミングが命です。
- 即効型の場合は、最後の服用から12時間後に採血します。
- 持続放出型の場合は、最後の服用から24時間後が基準です。
このルールを守らないと、濃度が高すぎたり低すぎたりして、誤った判断をします。たとえば、朝に薬を飲んで、その日の午後に採血したら、濃度が急上昇中で「高すぎ!」と誤診される可能性があります。
安定している患者は、3~6か月に1回の採血で十分です。でも、薬を変更した直後、年齢が変わったとき、腎機能に変化があったとき、または体調が急に悪くなったときは、1週間以内に再測定が必要です。

年齢や性別で、目標値は変わる
リチウムは腎臓で排泄されます。年を取ると、腎臓の働きが弱くなるので、同じ量を飲んでも血中濃度が上がりやすくなります。
- 40歳未満:0.8~1.0 mmol/L
- 40~60歳:0.6~0.8 mmol/L
- 60歳以上:0.4~0.6 mmol/L(一部の専門家は0.5~0.7 mmol/Lを推奨)
女性は、平均して男性より体重が軽く、腎臓のクリアランスも少し低いので、同年代でも10~15%少ない量で十分な場合があります。2024年の研究では、80歳以上の患者が、30歳未満の患者より1日平均437mgも少ない量で治療されていたことが示されています。
だから、年齢や体重、性別を無視して「全員に同じ量」を処方するのは危険です。特に高齢者では、血中濃度が0.6 mmol/Lを超えると、ふらつきや記憶力低下が起きやすく、転倒リスクが高まります。
他の検査も、リチウム治療には必須
リチウムは、腎臓だけでなく、甲状腺にも影響を与えます。約10%の患者で、甲状腺機能が低下して、疲れやすくなったり、体重が増えたりします。
だから、血中濃度の測定と同時に、毎年少なくとも1回は次の検査を受けてください:
- 血清クレアチニンとeGFR(腎機能)
- 甲状腺刺激ホルモン(TSH)
- ナトリウム、カリウム(電解質バランス)
2022年のガイドラインでは、腎機能の評価に「cystatin C」を併用することを推奨しています。クレアチニンだけでは、高齢者や筋肉量の少ない人の腎機能を過大評価してしまうからです。

ジェネリックの切り替えは、必ず医師と相談
薬局で「ジェネリックに変更しました」と言われても、勝手に受け取ってはいけません。
リチウムは、他の薬と違って、薬の「形」が変わると、効き方が大きく変わるのです。たとえば、持続放出型から即効型に変われば、血中濃度が急上昇して中毒になるリスクがあります。逆に、即効型から持続放出型に変われば、効果が弱まって発作が再発する可能性があります。
2024年の研究では、ジェネリックの切り替えで、4人の患者が血中濃度が危険なレベルまで上昇した事例が報告されています。すべて、薬の種類が変わった直後に起きました。
だから、ジェネリックに変更するときは、必ず次の3つを確認してください:
- 新しい薬は「持続放出型」か「即効型」か?
- 処方量(mg)は変わらないか?
- 変更後、1~2週間以内に血中濃度を測定する予定か?
もし「薬の名前が変わったけど、量は同じ」と言われても、血中濃度を測定しない限り、安全とは言えません。
今後の方向性:個別化治療へ
リチウムの治療は、単なる「量の調整」から、徐々に「個別化」へ進んでいます。
国際リチウム遺伝子研究(ConLiGen)は、30以上の遺伝子変異が、リチウムの効きやすさや排泄速度に関係していることを特定しました。今後、遺伝子検査と腎機能、年齢、体重を組み合わせて、AIが「あなたに最適なリチウムの量」を予測する時代が来ます。
すでに、いくつかの大学病院では、電子カルテのデータをもとに、自動でリチウムの調整提案をするシステムが試験導入されています。これで、血中濃度の乱れを防ぎ、副作用を減らすことが期待されています。
しかし、その技術が広まる前に、今私たちがすべきことは、シンプルです。ジェネリックを使っているなら、血中濃度を定期的に測ること。薬が変わったら、必ず測定すること。年齢や体調に合わせて目標値を見直すこと。
リチウムは、新しい薬がたくさん出ても、まだ「最も信頼できる」治療法の一つです。でも、その信頼は、血中濃度をきちんと管理するからこそ、成り立っています。
yuki y
ジェネリックに変えたらめっちゃふらついたんだよね。病院で測ったら1.4超えてた。薬屋の人に『同じ薬だよ』って言われたけど、全然違うわ。
Ryota Yamakami
俺も去年、ジェネリックに切り替えてからうつが悪化した。血中濃度測定してないって話だった。医者に怒られたけど、ちゃんと測定してからまた安定した。大事だよ、本当に。
Hideki Kamiya
ジェネリックは製薬会社の陰謀だよ。FDAもEMAも、全部大手と繋がってる。血中濃度の差って、実は故意に作られてるんだ。薬の効き目が安定しないから、また薬を買うんだよ。マジで詐欺。
Keiko Suzuki
リチウムの管理は、本当に丁寧さが命です。特に高齢の方は、腎機能の低下を考慮して、目標濃度を下げることが推奨されています。無理に同じ量を続けると、転倒や認知機能の低下につながります。安全第一でお願いします。
花田 一樹
ジェネリックで濃度が下がったって? ああ、それは普通。ブランドは薬の形が完璧に設計されてるから、ジェネリックは『似て非なるもの』。でも医者は『同じだ』って言うんだよね。笑っちゃう。
EFFENDI MOHD YUSNI
生物等価性? それは統計学的な嘘です。AUCとCmaxの80-125%という範囲は、『平均的には問題ない』というだけで、個体差を無視した危険な基準です。患者一人ひとりが実験台にされているのです。
JP Robarts School
この記事、製薬会社の広告だろ? ジェネリックを怖がらせて、ブランド薬を売りつけるためのプロパガンダ。血中濃度の話は本当だけど、それなら最初からジェネリックを禁止すればいいのに。
Mariko Yoshimoto
…あ、そういえば、最近のジェネリック、包装の文字がちょっと小さい気がする…。あれ、もしかして、成分の濃度も微妙に調整されてるの???????????????
HIROMI MIZUNO
高齢者の目標濃度、0.4〜0.6って聞いてホッとしました。母が1.0でずっと飲んでて、ずっとふらついてたの。今やっと下げて、転倒も減った! みんな、年齢に合わせて見直してね!
晶 洪
薬を変えるな。測定しろ。それだけ。
naotaka ikeda
僕は20年リチウム飲んでる。ジェネリックに変わったときも、測定してたから安心。大事なのは、薬の名前じゃなくて、血液の数値。
諒 石橋
日本はジェネリック推進しすぎて、患者を犠牲にしてる。欧米はちゃんと管理してるのに、こっちは『安いからOK』で済ませてる。情けない。
risa austin
本稿は、リチウム療法における、ジェネリック薬剤の生物学的等価性に関する、厳密な臨床的・薬動学的検討を基に、患者の安全性と治療の継続性を確保するための、包括的かつ体系的な提言をなしている。
Taisho Koganezawa
遺伝子検査で最適量をAIが提案する未来って、すごくない? 薬の量が『個人のDNA』で決まるって、SFみたいだけど、もうすぐ来るよね。
Midori Kokoa
朝の採血、12時間空けないとダメって、初めて知った。今度からちゃんと守る!
Shiho Naganuma
ジェネリックは安物。高齢者にそんなの飲ませるなんて、国が患者を軽視してる証拠。
Ryo Enai
ジェネリックは危険😱
依充 田邊
あー、リチウムの血中濃度って、まるで金のインゴットを溶かして、一人ひとりの血管に流してるみたいなもんだよ。ちょっと濃すぎたら死ぬ。ちょっと薄すぎたら壊れる。でも医者は『大丈夫』って言う。マジで笑えない。
Ryota Yamakami
yuki y さんのコメント、すごく共感した。俺も同じ経験した。薬局で『ジェネリックに変えました』って言われて、そのまま飲んだら、3日後にめまいと吐き気が止まらなくて救急搬送された。血中濃度1.45。医者に『測定してないの?』って怒られた。もう二度と、勝手に変えさせない。


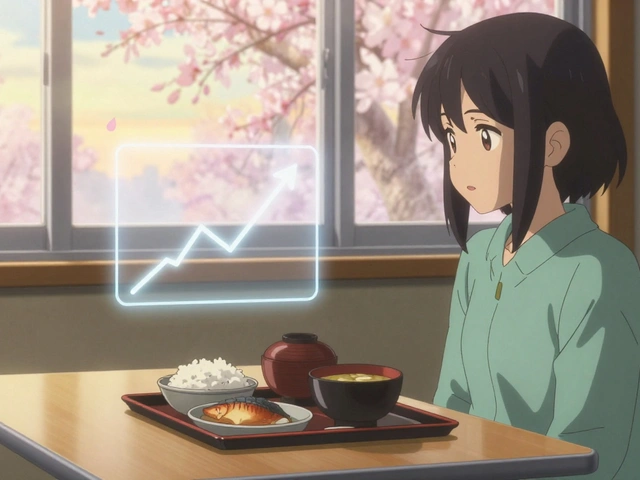
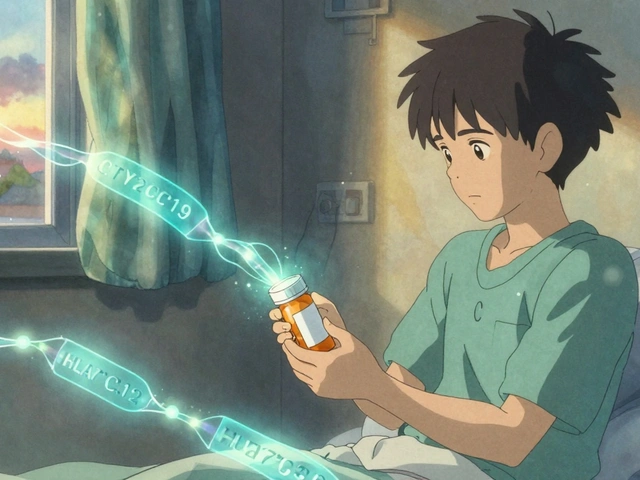
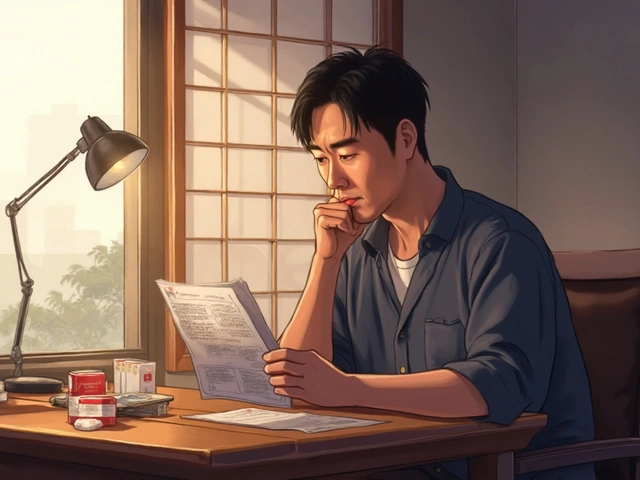
コメントを書く