
海外で薬を必要とするとき、あなたはどんな準備をしていますか?日本では当たり前のように手に入る薬が、海外では手に入らない、あるいは違法になっている可能性があります。アメリカでは処方箋なしで買える風邪薬が、日本やシンガポールでは厳しく規制されています。逆に、日本で規制されている薬が、タイやメキシコでは普通に売られていることもあります。この違いを知らずに旅行や海外移住を始めると、薬が没収されたり、病気の治療が中断されたり、最悪の場合には法律問題に巻き込まれることもあります。
海外で薬を手に入れる前に絶対に確認すべきこと
まず、あなたの薬が目的地の国で合法かどうかを確認しましょう。世界保健機関(WHO)の2025年ガイドラインによると、172カ国が麻薬に関する国際条約に加盟していますが、それぞれの国が独自に規制を設けています。たとえば、ヒドロコドンはアメリカでは処方箋薬ですが、日本では完全に禁止されています。一方、コデインはメキシコでは市販薬ですが、オーストラリアでは特別な許可が必要です。
この違いは、単なる薬の種類の問題ではありません。あなたが持っている薬が「麻薬」「向精神薬」「覚醒剤」に該当する場合、その扱いはさらに厳しくなります。アメリカで処方されるADHDの薬であるアムフェタミン・デキストロアンフェタミンは、ヨーロッパの多くの国で厳しく規制され、持ち込みには特別な許可書が必要です。シンガポールでは、14日分以上持ち込むと違法になります。日本では、麻薬類は30日分までが上限です。
これらの情報を得るには、国際麻薬統制委員会(INCB)の「旅行者向け国別規制データベース」を参照するのが最適です。2025年10月時点では、68カ国がこのデータを公開していますが、124カ国は情報がありません。つまり、あなたが行く国がリストにない場合、それは「リスクが高い」という意味です。
処方箋と薬の持ち込み:絶対に守るべきルール
海外で薬を合法的に持ち込むには、3つの基本ルールがあります。
- 薬は必ずオリジナルの容器に入れて持ち歩く
- 容器には処方箋のラベルが付いていること(患者名、薬名、用量、処方日が明記されている)
- 医師の説明書を携帯する(英語で、ICD-11コード付き)
このルールを守らないと、空港で薬が没収される可能性が高くなります。アメリカのTSAは2025年4月から、医療用液体薬(例:注射剤やシロップ)を3.4オンス以上持ち込んでも、事前に申告すれば許可する方針に変わりましたが、容器がオリジナルでない場合は即座に没収されます。
特に注意が必要なのは、フェノプロパン(風邪薬に含まれる)です。アメリカでは市販薬ですが、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦(UAE)では違法です。2025年第1四半期だけでも、シドニー空港で387件のフェノプロパンが没収されました。これは、麻薬の原料として使われる可能性があるためです。
現地で処方箋をもらうには?
海外で薬が足りなくなったとき、現地の医師に処方箋を出してもらうことは可能ですか?答えは「場合による」です。
ヨーロッパ連合(EU)では、2024年のデータによると、98.7%のケースでドイツやフランスの処方箋を別のEU諸国でそのまま使用できます。これは「ヨーロッパ処方箋」という仕組みのおかげです。しかし、アジアではまったく別です。タイでは、処方箋があればほとんどの薬が手に入りますが、マレーシアでは、ディアゼパムやアラゾラム(不安症の薬)は、どんなに処方箋があっても一切禁止されています。
現地で処方箋をもらうには、次の手順が必要です:
- 現地の医療機関を事前に調べる(IAMATネットワークの認定クリニックが信頼できる)
- 日本での診断書と処方箋のコピーを持参する
- 英語で説明できるように、薬のジェネリック名(例:「セトロプラミン」)を覚えておく
- 現地の医師に「日本ではこの薬を処方されていて、やめると体調が悪化する」と説明する
特に精神科の薬や鎮痛薬を必要とする人は、現地の医師が「日本で処方された薬と同等のもの」を出してくれないことがあります。その場合、代替薬を提案してもらう必要があります。

海外で薬が手に入らないときの対処法
2025年2月の調査によると、国際旅行者の中で41%が薬の不足を経験しています。特に、オピオイド系の鎮痛薬を必要とする人の67%が、海外で薬が手に入らなかったと報告しています。
そんなとき、どうすればいいでしょうか?
- 事前に余分に持っていく:90日分までなら多くの国で合法です。ただし、日本やシンガポールは例外です。
- 代替薬を調べる:たとえば、日本で使っている鎮痛薬が海外で手に入らないなら、イブプロフェンやアセトアミノフェンで代用できるか医師に相談しましょう。
- 現地の薬局に直接問い合わせる:薬局の薬剤師は、医師より早く薬の在庫状況を把握しています。日本語が話せる薬局もあるので、事前に調べておきましょう。
- オンラインサービスを利用する:MediFindやMyTravelMedのようなサービスは、28〜47カ国で薬の手配を支援しています。成功確率は85%(MediFind)と62%(MyTravelMed)と差がありますが、複雑な薬の場合は頼りになるでしょう。
旅行前にやるべき8つの準備リスト
薬のトラブルを避けるには、早めの準備が鍵です。平均して、複雑な薬(麻薬や向精神薬)の準備には18.7時間かかります。以下を90日前から始めましょう。
- 目的地の国が、あなたの薬を許可しているかをINCBのサイトで確認する
- その国の大使館にメールで問い合わせる(「旅行者向け薬持ち込み規制」について)
- 医師に「説明書」を書いてもらう(英語、ICD-11コード付き、処方日と用量を明記)
- 薬のラベルが日本語の場合は、英語または現地語の翻訳を公証人で取得する
- 薬をすべてオリジナル容器に入れ、ラベルが読める状態に保つ
- 処方箋のコピーを2〜3枚、バッグとスーツケースに別々に保管する
- 航空会社の薬持ち込み規則を確認する(TSA、JAL、ANAなど)
- 現地の認定クリニックを事前にリストアップしておく(IAMATのサイトで検索可能)
これらの手順を守れば、90%以上のケースで問題なく薬を手に入れることができます。逆に、この準備を怠ると、空港で薬を没収され、数日間の旅行を台無しにするリスクが高まります。
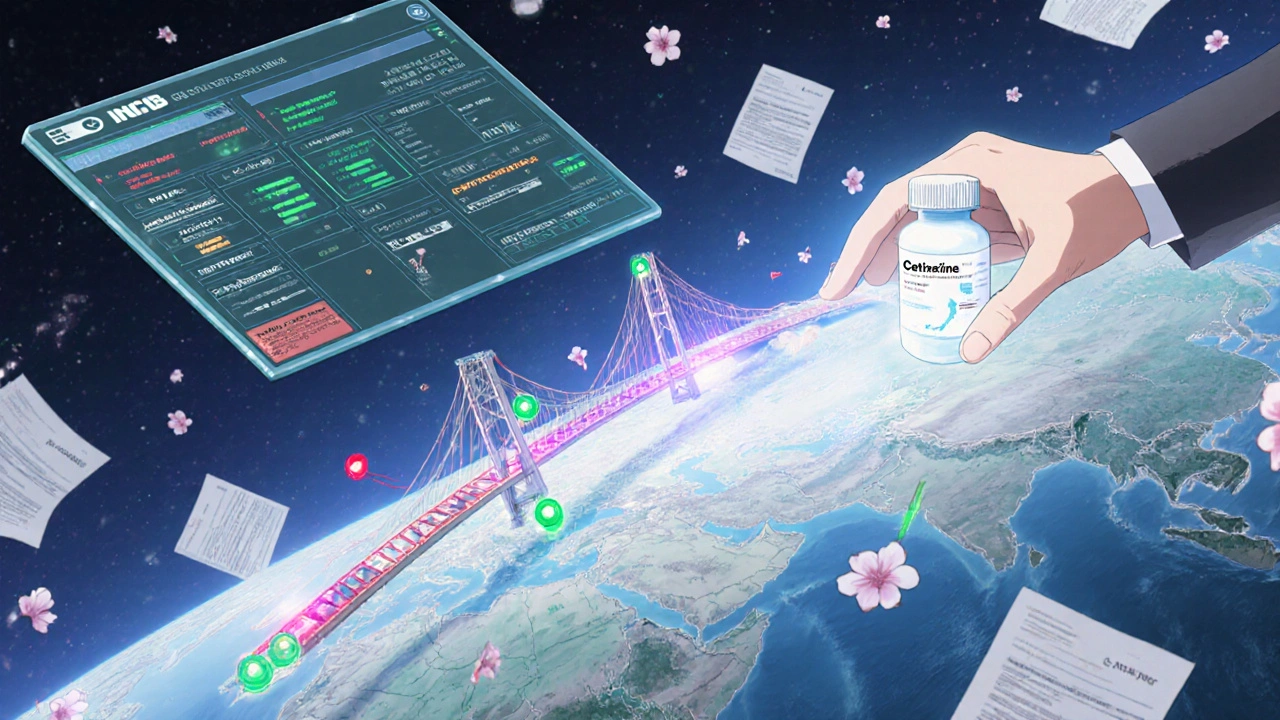
よくある失敗例と成功体験
Redditの旅行コミュニティでは、2025年9月に「ドバイでアムビエン(ゾルピデム)を没収された」という投稿が1,400件以上の高評価を集めました。投稿者は、医師の証明書を持っていても、UAEの税関で「許可が必要」と言われ、3日間の旅行を無駄にしたと書きました。
一方、ヨーロッパでは成功体験も増えています。あるユーザーは、ドイツの電子処方箋を使ってフランスでセトロプラミンを2時間以内に手に入れることができたと報告しています。EUのシステムは、処方箋が国境を超えて通用するため、とても便利です。
特に学生やビジネスパーソンに多いのが、ADHDの薬の問題です。アメリカの学生がヨーロッパで留学するとき、62%が処方箋が通らず、学業に支障をきたしています。これは、EUの規制がアメリカより厳しいためです。
今後はどう変わる?2026年からの新ルール
2026年からは、世界保健機関(WHO)が新しい国際的な薬の持ち込み書式を導入します。これは、どの国でも使える共通のフォーマットで、医師の説明書や処方箋の記載内容を統一するものです。これにより、言語の壁や書類の違いによるトラブルが減る見込みです。
また、アメリカでは2025年6月に「安全な海外処方薬輸入法」が下院で可決されました。2026年5月から、カナダ、英国、EU、スイスからアメリカに薬を輸入できるようになります。これは、アメリカ人が海外で薬を買うのを合法化する動きです。
日本でも、今後は海外の処方箋を認める方向に動く可能性があります。しかし、現時点では、日本の薬事法は依然として厳格です。海外で薬を手に入れるには、あくまで「自分の準備」が最重要です。
海外で処方箋を出してくれる医師は見つけられますか?
はい、見つけられます。国際医療支援団体(IAMAT)が運営する1,400カ所以上の認定クリニックを利用すると、英語で対応できる医師が見つかります。特に、日本語を話せる医師がいるクリニックも多数あります。事前にネットで検索し、予約を入れておきましょう。
日本で処方された薬を海外に持ち込むには、何枚までOKですか?
多くの国では「90日分」までが許可されています。ただし、日本では麻薬・向精神薬は30日分まで、シンガポールは14日分までが上限です。必ず目的地国の規制を確認してください。余分に持っていくのはリスクです。
風邪薬や痛み止めは持ち込みできますか?
一般的な風邪薬や痛み止め(イブプロフェン、アセトアミノフェン)は、ほとんどの国で持ち込み可能です。ただし、フェノプロパン(コンタックなど)はオーストラリアやUAEで禁止されています。成分表を必ず確認し、薬の名前をジェネリック(化学名)で覚えておきましょう。
海外で薬を買い直すと、日本と同じ効果がありますか?
ジェネリック薬なら、有効成分は同じなので効果はほぼ同じです。ただし、添加物や製造方法が違うと、体に合わないこともあります。特に精神科薬や抗てんかん薬は、少量の違いで効果が大きく変わるため、できるだけ日本で処方されたものを持ち込むのが安全です。
空港で薬を検査されたとき、どう対応すればいいですか?
薬をすべてオリジナル容器に入れて、医師の説明書と処方箋のコピーを手に持ってください。TSAや日本の保安検査では、薬を「医療用」として申告すると、優先的に検査してくれます。焦らず、丁寧に説明すれば、ほとんどの場合問題なく通れます。
依充 田邊
海外で薬を手に入れるって、まるでスパイ映画のオペレーションだよね?😂 『アムビエン持ってるけど、UAEでは違法です』って言ったら、税関のオッサンが『あ、それ、寝かせる薬?』って聞いてきたら、『はい、夢の中で世界征服するためです』って答えたら通るかな?
Rina Manalu
この記事は非常に丁寧に作られており、海外での薬の持ち込みに関するリスクを正確に伝えてくれています。特に、オリジナル容器と医師の説明書の重要性は、命に関わるため、必ず守るべきです。日本語のラベルだけでは、海外では全く意味を成さない場合が多いです。
Kensuke Saito
WHOの2025年ガイドラインって誰が書いたの?インボイスに書いてある数字だけ信用してたら、あとで痛い目見るよ。INCBのデータベースに載ってない国はリスク?じゃあ、南極の研究基地で薬が必要になったらどうすんの?
aya moumen
ああ…もう、これ読んだら泣きそう…。私のアダプトール、シンガポールでは14日分までって…。15日目からどうするの?! でも、でも、ちゃんと準備してたら大丈夫って書いてある…よね???😭😭😭
Akemi Katherine Suarez Zapata
フェノプロパンって、コンタックのやつ???あ、それ私いつも持って行ってた…。オーストラリアで没収されたって書いてあるけど、でも、なんか、それって…ちょっと、あんまりにも…悲しい。私も気をつけるわ。でも、みんな大丈夫だよね??
芳朗 伊藤
この記事、90日分までOKって書いてあるけど、日本では30日分までって明記してあるのに、なぜ「多くの国では」と曖昧に書くのか。曖昧な表現は、責任転嫁だ。医師の説明書にICD-11コードって、誰が書くの?日本語の診断書に英語でICD-11を手書きで書くんですか?
ryouichi abe
めっちゃ役に立った!特にIAMATのクリニックの情報、助かる!あ、でも、薬のジェネリック名って、セトロプラミンって書いてあるけど、私、それって「セルトラリン」って言ってた…。すみません…。みんなも、ちゃんと調べてね!
Yoshitsugu Yanagida
EUの電子処方箋が便利って?じゃあ、なんで日本はまだ紙の処方箋で50年も前から変わらないの?医者が手書きで「アムフェタミン」って書くの、2025年だよ?
Hiroko Kanno
おお、これ、めっちゃ参考になる!ありがとう!でも、ちょっとだけ…「オリジナル容器」って、薬の袋のままじゃダメなの?それって、全部ビンに移さなきゃなの?ちょっと面倒だな~
kimura masayuki
海外で薬を手に入れるために、日本人がここまで神経質になるなんて、日本が弱すぎだろ。薬が足りない?なら、日本に戻ればいい。海外で病気になるなんて、自己責任。アメリカのADHD薬が通らない?それは、日本の薬が優れてる証拠だ。西洋の薬に頼るな、日本精神で乗り切れ!





コメントを書く